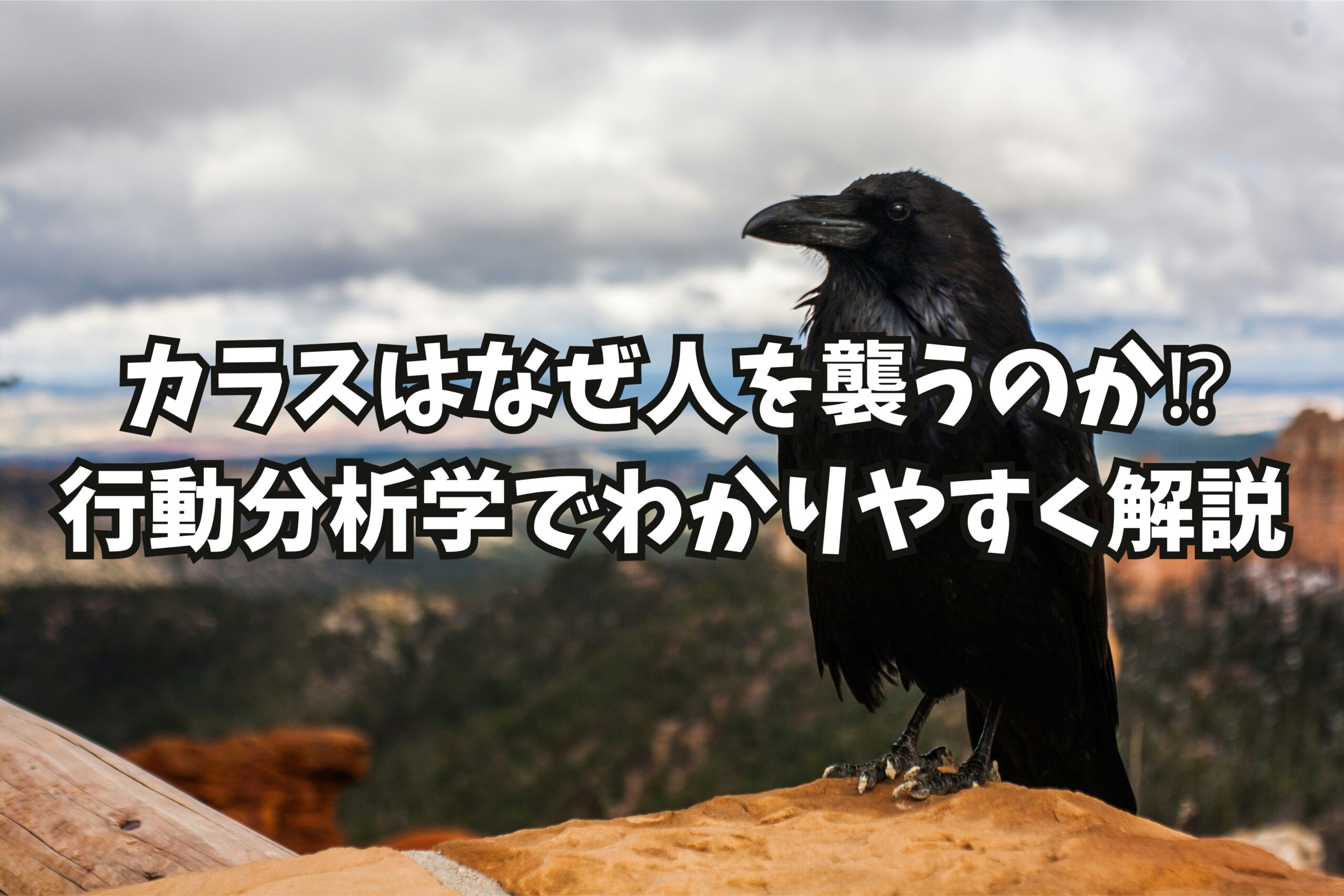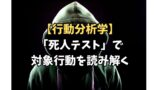カラスといえば今や日本人に最もなじみ深い鳥といえるのではないでしょうか。
街を歩いていて見かけない日はありませんよね。
しかし、近年ではそんなカラスに襲われる人が続出しています。
なぜカラスは人を襲うのか?
その行動を行動分析学という観点から解説します。
ヒトや動物の行動の原因を解明し、行動に法則を見出すことを目的とした心理学のひとつ。
医療や介護、スポーツ、ビジネス、教育、家庭など様々な場面で応用されています。

ケンさん(アニマルトレーナー)
アニマルトレーナー歴15年。
行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。
「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。
日本人になじみ深いカラスという鳥
一口に「カラス」といっても実は日本には多くの種類のカラスがいます。
その中でも特に目にする機会の多いカラスがハシブトガラスとハシボソガラスという種類のカラスです。
ハシブトガラス:日本全国で最もポピュラーなカラス。都市部から山間部まで、幅広い環境に生息しています。

ハシボソガラス: ハシブトガラスより体格が小さく、分布も限られています。主に山間部や森林地帯に生息しています。

この2種類のカラスは、どちらも非常に知能が高く、人間と共存している姿がよく見られます。
ゴミを漁ったり、フンをまき散らしたりして、生活環境を悪化させることもある一方、害虫を食べてくれたり、動物の死骸を処理してくれたりするという、益鳥としての側面もあります。
なぜカラスは人を襲うのか?
カラスに「お弁当やおかしを奪われた」「追いかけられた」、という経験をしたことがある人も少なくないのではないでしょうか?
なぜカラスは人を襲うのか、行動分析学を使って考えてみましょう。
対象行動を設定する
まず行動を分析するにあたって最初にやらなければいけないことは、対象行動は何かを考えることです。
行動には死人にはできないことすべてという定義がありますので注意してください。
ここではカラスの攻撃行動を対象行動として考えていきます。
行動の随伴性はなにか
対象行動をはっきりさせたら、次は「その行動がなぜ起こるのか」という随伴性を考えていきましょう。
「○○したら△△が起きる」という環境と行動との関係。
環境とはその行動を取り巻くすべての事象のこと。
カラスは人へ攻撃行動をしているので、この攻撃行動は強化されているといえます。
行動の出現頻度が増えること
強化には正の強化と負の強化という2種類あります。
正の強化:行動の直後に良いことがあることで、行動の出現頻度が増えること。
負の強化:今まであった悪いことが、行動の直後に取り去られることで、行動の出現頻度が増えること。
理由その①|食べ物をゲットするため(正の強化)
カラスが人を襲う理由その①は「食べ物をゲットできるから」です。
随伴性としては
食べ物無し → 攻撃行動 → 食べ物あり
攻撃行動の直後に「食べ物」という好子が現れたので、この攻撃行動は強化されました。
これはわかりやすいですよね。
理由その②|巣やヒナを守るため(負の強化)
カラスが人を襲う理由その②は「巣やヒナを守るため」です。
随伴性としては
巣やヒナへの脅威あり → 攻撃行動 → 巣やヒナへの脅威なし
攻撃行動の直後に「巣やヒナへの脅威」という嫌子が取り去れたので、この攻撃行動は強化されました。
行動の原因がわかれば適切な対策ができる
行動の原因がわかれば、問題行動への対策ができるようになります。
カラスが食べ物を狙っているのであれば、カラスが周辺にいる状況下で食べ物を出すのは止めましょう。
一度人間から食べ物を取ったカラスは、次々と人を襲うようになります。
その場しのぎで、食べ物を放棄して逃げるのも極力避けましょう。
新たな被害者を出すことになってしまいます。
人を襲うカラスを育ててしまっているのは、我々人間なのかもしれません…
カラスが巣やヒナを守ろうと敏感になっているのであれば、行政や自治体で看板を立てるなどして周知させるというのも対策の一つです。
カラスが脅威を感じていないのであればそもそも攻撃行動は出現しないのですから。
特に春から初夏にかけてはカラスの繁殖期になっていますので注意が必要ですよ。
まとめ
行動には必ず原因があります。
行動分析学でその行動の原因を解明し、理解することができたなら、この世界はもっとより良く、素晴らしいものにできるはずです。
みなさんも、身近なあの人、あの動物の行動を深く考えてみませんか?