行動分析学は人や動物の行動がどういう原理で起こっているかを明らかにすることを目的としています。
行動に直後に良いことが起きればその行動は再び起こりますし(強化)、逆に悪いことが起こればその行動は減ります。(弱化)
行動分析学は問題行動へのアプローチにもよく用いられます。
この記事ではそのうちのひとつ、抹殺法について解説していきます。

ケンさん(アニマルトレーナー)
アニマルトレーナー歴15年。
行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。
「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。
抹殺法とは
抹殺法…
非常に物騒な響きですよね。
抹殺法とは、「問題行動を引き起こす刺激そのものを消し去ってしまおう!」という方法です。
タバコが止められない?タバコを捨ててしまえばいい。
スマホを手放せない?スマホを壊してしまおう。
息子がゲームばかりする?これも捨ててしまおう。
犬がゴミ箱をあさるなら、部屋にはゴミ箱を置かないようにしよう。
トラブルばかり起こす部下は解雇だ!
このように抹殺法を使えば問題行動はパーフェクトに解決します。
抹殺法は問題行動に対して確実で効果の高い方法だといえるでしょう。
ですがみなさんお気づきの通り、決して最善の方法ではありません。
抹殺法の欠点
抹殺法を使えばしばらくの間、問題行動は100%無くなります。
そう、しばらくの間。
抹殺法の欠点は、問題行動を起こす本人には何も新しい随伴性を与えていないので、要素がそろえばまた問題行動を始めるという点です。
タバコが手に入ればまた吸うし、スマホやゲームだって同じことです。
抹殺方法の賢い使い方は、スポット的に使うことです。
例えば
勉強するときはゲーム機を親に預ける。
恋人と会う際にはスマホの電源を切る。
飼い主が不在にする時はゴミ箱を片付ける。
といったように。
抹殺法を上手に活用できれば、問題行動をある程度減らすことができるはずです。
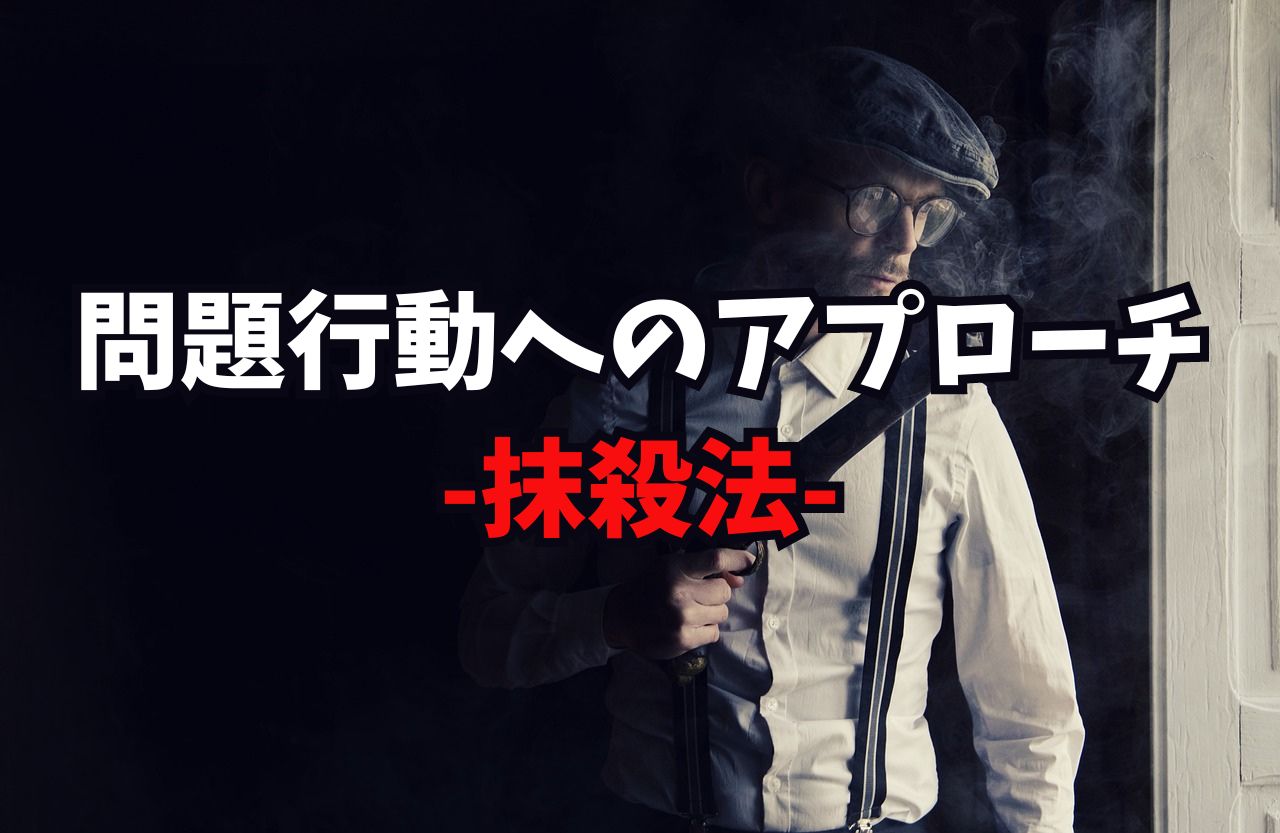



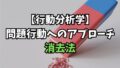
コメント