こんにちは!ケンさんです!
行動分析学を学び始めた皆さん、勉強は順調ですか?
今回は、私たちにとって身近な「ゲン担ぎ」や「おまじない」といった行動が、なぜやめられないのか、その理由を行動分析学の視点から考えてみましょう。
ヒトや動物の行動の原因を解明し、行動に法則を見出すことを目的とした心理学のひとつ。
医療や介護、スポーツ、ビジネス、教育、家庭など様々な場面で応用されています。

ケンさん(アニマルトレーナー)
アニマルトレーナー歴15年。
行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。
「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。
そもそも「迷信行動」って何?
「迷信行動(superstitious behavior)」という言葉を聞いたことはありますか?
これは、行動と結果の間に本当は因果関係がないのに、偶然の一致によって、その行動が繰り返されるようになる現象のことです。
この考え方は、行動分析学の創始者であるB.F.スキナーが行った有名な実験で発見されました。
スキナーはハトに一定時間ごとにエサを与える実験をしました。
すると、ハトはたまたまエサが出た時に行っていた行動(例えば、首を振る、片足で回るなど)を、エサをもらうための行動だと勘違いし、それを繰り返すようになったのです。
ハトの行動は、エサとはまったく関係がありませんでした。
しかし、ハトは「この行動をしたからエサが出た」と誤った因果関係を学習してしまったのです。
これが、迷信行動の正体です。

私たちの「ゲン担ぎ」も同じ原理
このハトの実験と同じことが、私たちの日常生活でも起きています。
- 「試合の前に必ずこの靴下を履く」
ある試合で、たまたまその靴下を履いていた時に勝てた。その成功体験が偶然に結びつき、次からもその靴下を履くようになった。 - 「試験の朝に特定の儀式を行う」
以前、その儀式を行った時に良い点数が取れた。その偶然の成功が、儀式を繰り返す理由になった。
これらは、ハトの実験と同じように、行動と好ましい結果が偶然に結びついたことで、その行動が強化され、習慣化された「迷信行動」なのです。
強化:行動の出現頻度が上がること
迷信行動のメリットとデメリット
では、この迷信行動にはどんな意味があるのでしょうか?
メリット
迷信行動には、実は無視できないメリットがあります。
それは「安心感」を与えてくれるということです。
私たちは、試験や試合のような、結果がどうなるか分からない状況に直面すると不安になりますよね。
そんな時、特定の行動をすることで「自分はできる限りのことをやったんだ!」と感じ、心理的な安定を得ることができます。
この安心感は、本番での集中力やパフォーマンスを高めることにつながることもあります。
デメリット
一方で、迷信行動にはデメリットもあります。
迷信行動に頼りすぎると、根本的な問題解決から目をそらしてしまう可能性があります。
例えば、試験の点数が上がらない本当の原因が、勉強不足や苦手分野にあるにもかかわらずに「おまじないが足りなかったからだ」と考えてしまう…といった具合です。
これでは、本当の成長機会を逃してしまいます。
また、迷信行動ができない状況になると、強い不安を感じたり、ストレスになったりすることもあります。
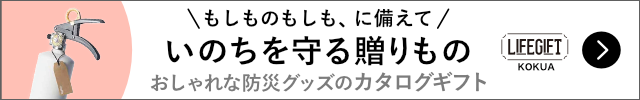
まとめ
「ゲン担ぎ」や「おまじない」は、一見すると非合理的な行動に思えます。
しかし、行動分析学の視点から見ると、それは偶然の成功によって強化された、私たちの心のセーフティネットのようなものだと言えます。
迷信行動は、私たちに一時的な安心感を与えてくれますが、頼りすぎると成長の妨げになることもあります。
この両面を理解することが、行動分析学を学ぶ上でとても面白いポイントになります。
皆さんも身の回りの「迷信行動」を探してみて、その行動がどんな結果と偶然に結びついているのか、ぜひ考えてみてくださいね。

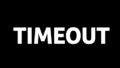

コメント