太郎は、代理権の基礎をしっかりと理解し、先輩の佐藤さんに新たな疑問を投げかけた。
「佐藤さん、よく聞く言葉に『無権代理』ってあるじゃないですか。これは、代理権がない人が契約を結ぶってことですよね?でも、その契約って、必ず無効になるんですか?」
佐藤さんは、太郎の熱心な姿勢に満足そうに頷き、
「良い質問だね。無権代理の契約が有効になる場合もあるんだ。」
と答えた。
「え、有効になるんですか?」
太郎は驚いた。
「そうなんだ。それが、不動産取引の面白いところでもあるね。無権代理の契約が有効になるには、いくつかの条件が揃う必要がある。まず、相手方が、その人が代理人だと信じるに足りる『表見』があったこと。そして、相手方が、その人が代理人だと信じて、契約を結んだこと。つまり、相手方が『善意』かつ『無過失』であったことが必要なんだ。」
善意:ある事実を知らないこと
悪意:ある事実を知っていること
佐藤さんは、さらに詳しく説明を始めた。
「例えば、AさんがBさんに土地を売却したいと依頼したとしよう。そのBさんは、今度はCさんにその土地の売却を依頼した。しかし、実際には、BさんにはCさんに売却を依頼する権限はなかったとする。この場合、Cさんが、Bさんに売却を依頼する権限があると信じて、Dさんと土地の売買契約を結んだとしたら、この契約は有効になる可能性があるんだ。」
太郎は、複雑な状況に頭を悩ませた。
「でも、なんで無権代理の契約が有効になるんですか?」
佐藤さんは、丁寧に説明した。
「これは、取引の安全を守るための例外的なルールなんだ。もし、全ての無権代理の契約が無効となってしまうと、取引の相手方は、常に相手が本当に代理権を持っているかどうかを慎重に確認しなければならなくなる。そうなると、取引が非常に煩雑になり、経済活動が停滞してしまう恐れがあるんだ。そこで、一定の条件の下では、無権代理の契約を有効とすることで、取引の円滑化を図っているんだ。」
佐藤さんは、話を変えて、「善意」と「悪意」について説明した。
「『善意』とは、ある事実を知らないことをいい、『悪意』とは、ある事実を知っていることをいう。さっきの例でいうと、Cさんが、Bさんに売却を依頼する権限がないことを知っていたとしたら、Cさんは悪意であり、この場合、契約は無効となるんだ。」
太郎は、佐藤さんの説明を聞きながら、ノートにメモを取り始めた。
「つまり、無権代理の契約が有効になるためには、相手方が、代理権があることを信じるに足りる状況で、善意かつ無過失で契約を結んだことが必要ってことですね。」
佐藤さんは、太郎の理解を確かめながら、
「そうだね。ただし、無権代理の契約は、原則として無効なので、安易に無権代理の行為を行ってはいけない。もし、無権代理の行為を行ってしまった場合は、本人がその損害を賠償しなければならなくなる可能性があるんだ。」
太郎は、佐藤さんの話を聞いて、無権代理の複雑さを改めて実感した。
「佐藤さん、今日は本当にありがとうございました。無権代理について、よくわかりました。」
佐藤さんは、にこやかに微笑み、
「太郎くんは、本当に勉強熱心だね。これからも頑張ってね。」
と励ましの言葉をかけた。
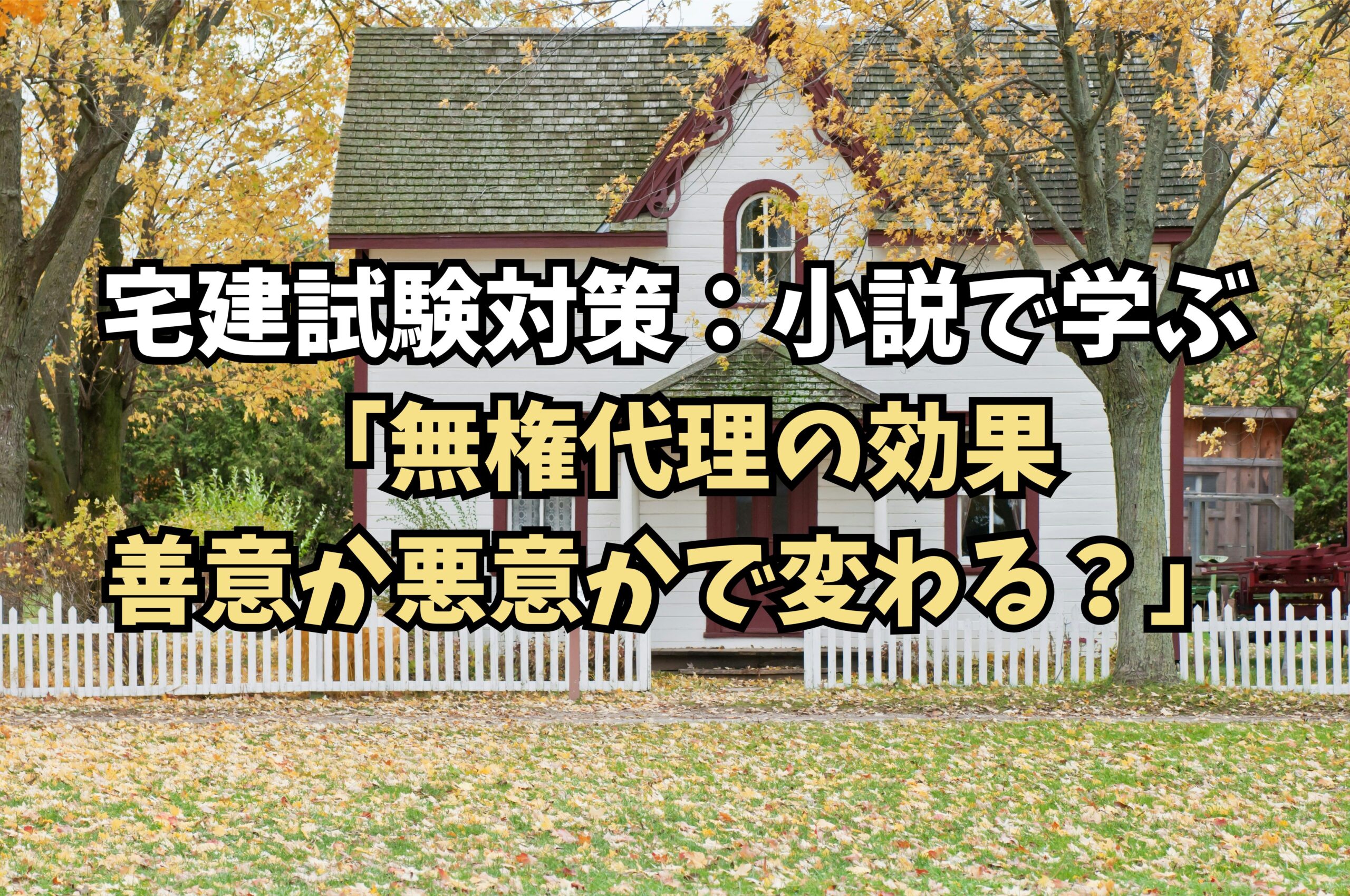



コメント