みなさんは子どもや後輩、部下、あるいは先輩上司など、身近な人間の問題行動に困っているという経験はありませんか?
もしかしたらペットの問題行動に悩まされている人もいるかもしれませんね。
行動分析学では、望ましくない行動は減らし、望ましい行動を増やすために様々な手法が用いられます。
その一つが「分化強化」と呼ばれる手法です。
分化強化には、代替行動分化強化(DRA)、他行動分化強化(DRO)、低頻度行動分化強化(DRL)などがあります。
今回は、他行動分化強化(DRO: Differential Reinforcement of Other Behavior)について、その仕組みや特徴、具体的な活用方法などを詳しく解説していきます。

ケンさん(アニマルトレーナー)
アニマルトレーナー歴15年。
行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。
「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。
DROとは?
DRO(Differential Reinforcement of Other Behavior)は、他行動分化強化といい、行動分析学でよく用いられる行動変容の手法のひとつです。
問題行動ではなく、問題行動以外の全ての行動を強化することで、間接的に問題行動を減らしていくことを目指します。
なぜDROが効果的なの?
ここからはDROのメリットや効果をご紹介します。
相手に与えるストレスが小さい
DROは問題行動以外の行動を強化するという手法のため、怒鳴ったり叱ったり、あるいは叩いたりといったネガティブな刺激は使いません。
相手にストレスを与えることなく行動修正ができるので、相手との関係性が壊れるリスクも少ないです。

問題行動を消去できる
行動修正を行うときにやりがちなのは、問題行動を意図せず強化してしまうということです。
問題行動に対して注意や叱責したりすることは、その問題行動を強化してしまう可能性があるのです。
注意や叱責を含む注目は行動を強化する場合があります。
DROでは問題行動は基本的に無視ですので、問題行動を助長するリスクが少ないのが特徴です。
DROの実践方法
それではDROの実践方法を具体的に見ていきましょう。
目標行動の設定
まずは減らしたい問題行動を具体的に定義し、その代わりに増やしたい行動(目標行動)を明確にします。
例:問題行動「乱暴な口調」→目標行動「優しい口調」
問題行動「廊下を走る」→目標行動「廊下を歩く」
強化の準備
問題行動と目標行動が明確になったら、次は効果的な好子を準備します。
好子は、人や動物によって異なりますが、好きなおもちゃ、お菓子、ゲームやお金など、その個体にとって強化的なものを選ぶと効果的です。
その個体が好きなもの・出来事
強化スケジュールの設定
強化の準備ができたら、次はどのくらいの頻度で好子を与えるかを決めます。
最初は短い間隔で好子を与え、徐々に間隔を延ばしていくと効果的です。
一貫性のある実施
DROを実施する時は、対象の人や動物にかかわる人間が全員同じルールを共有することが重要です。
学校内での生徒の問題行動であれば教師全員が、ペットに関する問題行動であれば飼い主やトレーナー全員が同じ意識をもって問題行動と向き合わなければいけません。
実践例 乱暴な言葉使い
それではDROの手順を見ていきましょう。
問題行動は「乱暴な言葉使い」
DROは問題行動以外の行動を強化する手法ですので、乱暴な言葉以外の行動を強化していきます。
まずDROを始める前に、乱暴な言葉使いとは何かを具体的に定義付けて、関係する人同士で共有しましょう。
例えば、声のボリュームや喋り方、語尾などです。
乱暴な言葉で話しかけられたときは「ふぅん」とか「へぇ」とか「そうなんですね」など最低限の返答にとどめます。
そして乱暴な言葉以外で話しかけられた時は、しっかりと目を見て、笑顔でリアクションしてあげましょう。
何かをしてもらったり、やってくれたりしたときも同様に良いリアクションをしてあげます。
とにかく問題行動以外の行動に対しては良いリアクションで答えてあげてください。
そうすれば問題行動である「乱暴な言葉使い」は徐々に出現頻度を減らしていくはずです。
DROのポイント
つづいてはDROを実践する際のポイントを解説します。
問題行動には反応しない
問題行動が出た時は、特に何もせず、静かにやり過ごしましょう。
下手に注意したり叱責したりするのは、問題行動を強化してしまう可能性があります。
問題行動には注目せずに無視するのが鉄則です。
※あくまで問題行動を無視するのであって、個人や個体を無視しないよう注意しましょう。
目標行動への即時強化
目標行動が出た直後に、好子を与えます。
これは60秒ルールという考え方で、対象行動の出現から好子の提示までの時間が長くなるほど、その効果は薄まるというものです。
好子は望ましい行動が出た時、なるべく早く提示しましょう。
好子の多様化
同じ好子ばかりではなく、様々な種類の好子を取り入れるとさらに効果的です。
DROの注意点
良いこと尽くしのようなDROですが気を付けなければいけないポイントもあります。
実はDROはその特性上、問題行動を減らすのに時間がかかるといわれています。
なので実際はDRO単独ではなく、他の方法(DRAやDRIなど)と組み合わせて使うことが多いです。
DRI:対立行動分化強化のこと。問題行動とは物理的に両立しえない行動を強化する手法。
DRA:代替行動分化強化のこと。今ある問題行動に代わる、望ましい行動を強化する手法。
まとめ
DROは、問題行動を改善するための有効な手法の一つです。
しかし、個々の状況に合わせて適切に実施することが重要です。
このブログが身近な人やペットの問題行動を改善する一助になれば幸いです。

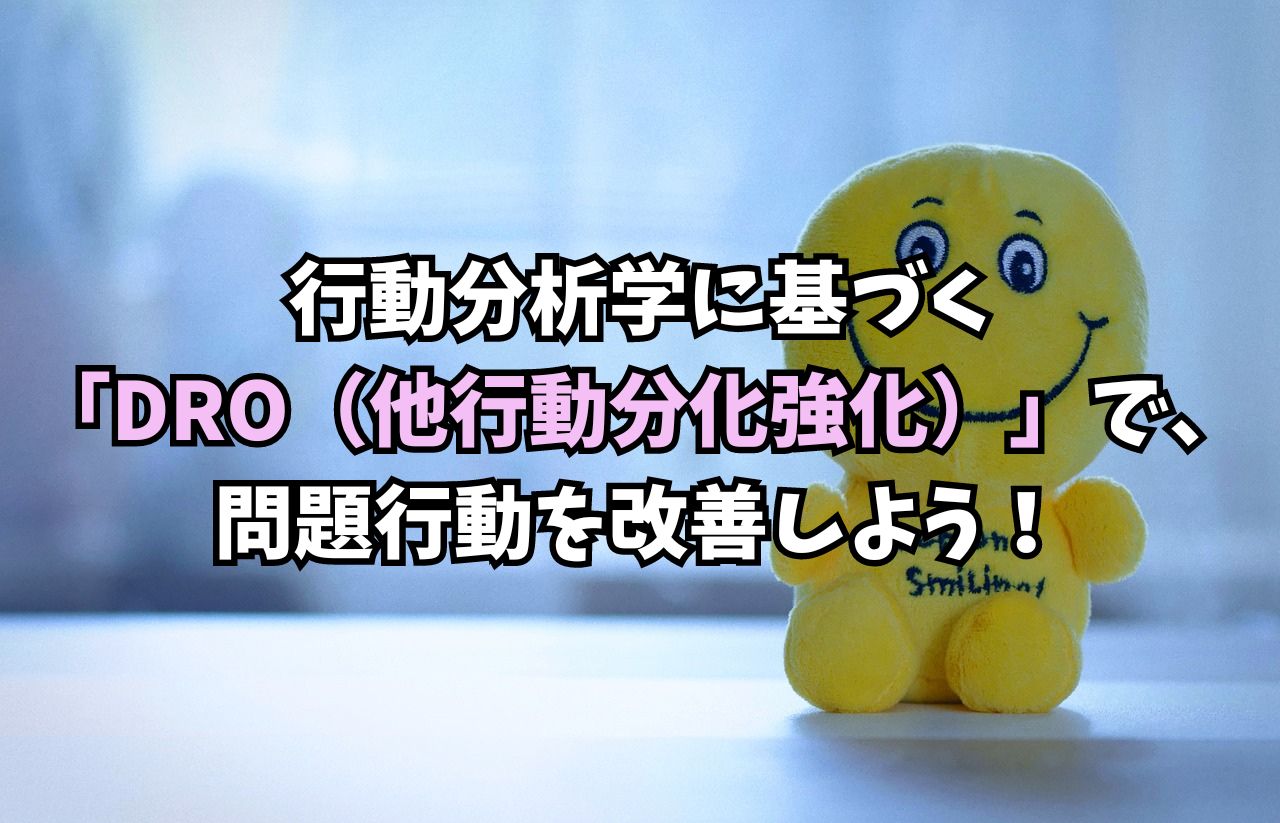


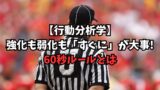


コメント