こんにちわ!ケンさんです!
動物のトレーニングを続けていると、「なぜか分からないけど、この行動をすると良いことが起きる」と、動物が思い込んでいるような行動に出会うことがあります。
例えば…
- おやつをもらう前に、必ず左足を上げる犬
- ケージに入るときに、鼻を鳴らすウサギ
こうした行動は「迷信行動」と呼ばれ、トレーナーの意図とは関係なく偶然に強化された結果、定着してしまったものです。
この迷信行動を理解し、効果的に修正するための方法を、行動分析学の観点から解説します。

ケンさん(アニマルトレーナー)
アニマルトレーナー歴15年。
行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。
「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。
なぜ迷信行動が生まれるのか?
迷信行動は、特定の行動とその後に偶然生じた報酬(強化子)との間に、実際には因果関係がないにもかかわらず、動物が「関連がある」と学習してしまうことで起こります。
例えば、ケージに入ったウサギが偶然鼻を鳴らした直後、飼い主さんがおやつをあげたとします。
この偶然の一致が何度か続くと、ウサギは「ケージに入る前に鼻を鳴らすと、おやつがもらえる」と勘違いし、その行動が習慣化してしまうのです。
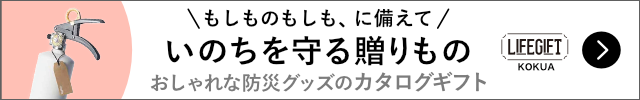
迷信行動を「消去」するトレーニングの3ステップ

ステップ1:行動の「機能」を理解する
まず、なくしたい行動がどのような強化子によって維持されているかを特定します。
行動の直後に何が起こっているか、注意深く観察しましょう。
行動の機能分析の例
| A (Antecedent: 先行条件) | B (Behavior: 行動) | C (Consequence: 結果) | 機能 (Function) |
| 飼い主が部屋を出ようとする | 犬が吠える | 飼い主が立ち止まって声をかける | 注意獲得 (Attention) |
| おやつの時間になる | 猫が特定の場所で鳴く | 飼い主がおやつをあげる | 要求 (Access to tangibles) |
| 来客がくる | 犬がゲストに飛びつく | ゲストが撫でてくれる | 注意獲得 (Attention) |
| ドッグランに行く | 犬がリードを引っ張る | 犬が好きな匂いを嗅ぐことができる | 感覚的強化 (Sensory reinforcement) |
| 訓練中に指示を出す | 犬が地面に体をこすりつける | 指示が中断される | 回避・逃避 (Escape) |
| 飼い主がボールを投げる | 犬がボールをくわえて持ってくる | 飼い主が再度ボールを投げる | 遊ぶこと (Play/Access to activities) |
この分析によって、動物がその行動を続ける理由(機能)が明確になります。
ステップ2:強化子を「除去」する
次に、特定した強化子を取り除くことを徹底します。
先ほどの例であれば、「鼻を鳴らす」という行動がおやつをもらうための行動だと動物が学習しているため、「鼻を鳴らした」直後には、たとえおやつをあげる予定だったとしても、それは一時的に見送ります。
このステップで注意すべきは、「消去バースト」という現象です。
これは、動物が「あれ、いつもと違うな?」と感じ、いつも以上に強く、頻繁に問題行動を繰り返す時期です。
ここで根負けして強化子を与えてしまうと、かえって迷信行動が強固になってしまうため、一貫した対応が不可欠です。
ステップ3:望ましい「代替行動」を教える
ただ単に問題行動をなくすだけでなく、望ましい代替行動を教え、それを強化することが成功のカギです。
例えば「ケージに入って座る」という望ましい行動を教え、それができたらすぐに褒めたり、おやつをあげたりします。
これにより、動物は「鼻を鳴らしても意味がないけれど、座れば良いことが起きる」と新しい学習をし、より効率的な行動に置き換わっていきます。
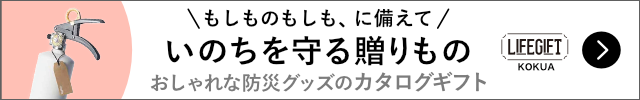
まとめ
迷信行動の修正は、根気と一貫性が求められる作業です。
しかし、行動の機能を見抜き、適切な方法で修正することで、動物は無駄な行動を減らし、より効率的で満足度の高い行動を身につけることができます。
もし、あなたのトレーニングセッションで「なぜか分からないけど、この行動をするな…」と思うことがあれば、ぜひこの3つのステップを試してみてください。
きっと、新たな発見があるはずです。






コメント