こんにちは!ケンさんです。
今回は行動分析学の中でも少しややこしい「価値変容の原理」について、皆さんが抱くであろう疑問を解消しながら、レスポンデント条件付けとの違いも解説していきたいと思います。

ケンさん(アニマルトレーナー)
アニマルトレーナー歴15年。
行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。
「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。
価値が変わる?「価値変容の原理」とは
皆さんは、普段何気なく手に取るものや、耳にする音、かけられる言葉に、様々な「価値」を感じていると思います。
例えば、お小遣い(お金)は欲しいものを買えるから嬉しい、先生からの褒め言葉は認められた気がして頑張れる、など。
でも、ちょっと考えてみてください。
生まれたばかりの赤ちゃんにとって、お金はただの紙切れです。
褒め言葉の意味もまだ理解できません。
では、なぜこれらは私たちにとって価値のあるものになったのでしょうか?
ここに「価値変容の原理」という行動分析学の考え方が関わってきます。
価値変容の原理とは、もともと私たちにとって中性的な刺激(中性子)が、オペラント条件付けにおける好子や嫌子としての機能を持つようになる現象のことを指します。
具体例で見てみよう!
いくつかの例を通して、価値変容の原理をさらに深く理解していきましょう。
例1:子どもへのご褒美
- 初期
子どもは初めてお金をもらっても、その価値は理解できません。
つまりお金は中性子です。 - 介入
おこづかいをあげて、実際にお金を使って買い物をする経験をさせます。 - 価値変容
最初は価値のなかったお金ですが、子どもにとって嬉しいもの、価値のあるものとして認識されるようになります。
二次的な強化子(条件性強化子)へと価値を変えたお金は、子どもの行動を強化することができます。
例2:犬に対する褒め言葉
- 初期
「良い子だね」「すごいね」といった言葉は、最初は犬にとって特別な意味を持たない単なる音の響きです。 - 介入
これらの言葉を、犬が喜ぶおやつ、優しく撫でる時、同時に使います。 - 価値変容
褒め言葉を聞くだけで、犬は「良いことが起こるかもしれない」と期待するようになり、その言葉自体が犬の行動を強化する力を持つようになります。
ここがポイント!レスポンデント条件付けとの違い
ここで、経験によって刺激が意味を持つようになるという点で似ている「レスポンデント条件付け(古典的条件付け)」との違いをしっかり理解しておきましょう。
レスポンデント条件付けって何?
レスポンデント条件付けとは、もともと何の関係もなかった二つの刺激が、繰り返し一緒に提示されることで、一方の刺激がもう一方の刺激と同じような反応を引き起こすようになる学習のことです。
「パブロフの犬」というお話が有名ですね!
パブロフの犬の実験
- 犬に肉片(無条件刺激)を与えると、唾液が出る(無条件反応)のは自然な反応。
- 餌を与える直前にいつもベルの音(中性刺激)を聞かせることを繰り返す。
- すると、ベルの音(条件刺激)を聞かせただけで、犬が唾液を出すようになる(条件反応)。
つまり、もともと無関係だったベルの音が、肉片と結びつけられることで、餌と同じような唾液分泌反応を引き起こすように学習される、というのがパブロフの犬の実験です。
| 項目 | レスポンデント条件付け (古典的条件付け) | 価値変容の原理 |
|---|---|---|
| 学習の対象 | 生理的な反応や感情反応など、反射的で不随意な行動(レスポンデント行動) | 自発的に行われるオペラント行動 に影響を与える刺激の価値の変化 |
| 学習の成立 | 中性刺激と無条件刺激の対提示 (例:ベルの音と肉片) | 中性刺激と好子や嫌子の対提示 (例:褒め言葉とお金) |
| 反応の種類 | 中性刺激がレスポンデント行動を引き起こすようになる | ある刺激が、好子や嫌子として機能するようになる |
| 例 | 餌の前にベルを鳴らすと、ベルの音だけで唾液が出るようになる(パブロフの犬) | 一生懸命働くとお金がもらえ、お金で欲しいものが買えるようになる |
レスポンデント条件付けでは、特定の刺激が別の刺激と結びつくことで、感情や生理的な反応が引き起こされるようになります。
一方、価値変容の原理では、ある行動をした結果として得られた刺激が、その後の行動の頻度を変化させる力を持つようになることであり、その刺激は必ずしもレスポンデント行動を引き起こすとは限りません。
まとめ
今回のブログ記事では、行動分析学における重要な概念の一つである「価値変容の原理」について解説しました。
価値変容の原理
行動の結果と結びつくことで、刺激がオペラント行動に影響を与える価値を持つようになる。
レスポンデント条件付け
刺激と刺激の対提示によって、感情や生理的な反射反応が条件付けられる。
これらの違いを理解することで、行動分析学の面白さがさらに深まるはずです。
これからも一緒に、行動分析学の奥深い世界を探求していきましょう!
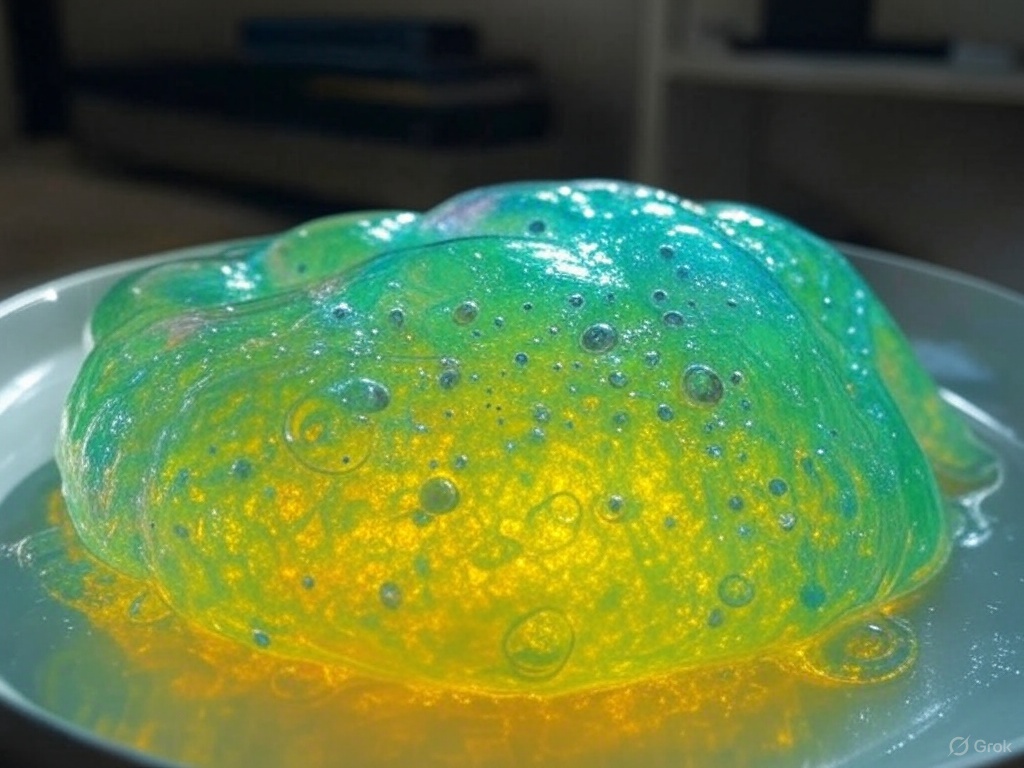


コメント