こんにちは!ケンさんです。
みなさんは「怒り」という感情をうまくコントロールできていますか?
近年、カスハラやモラハラといった様々なハラスメントが増加傾向にあります。
僕自身も、怒りを抑えられない人が多いのではないか?と感じています。
今回は、怒りの感情に悩まされている方に向けて、「DRI(対立行動強化法)」という行動分析学の手法を用いたアンガーマネジメントについて解説していきます。

ケンさん(アニマルトレーナー)
アニマルトレーナー歴15年。
行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。
「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。
DRIとは
DRI(Differential Reinforcement of Incompatible Behavior)とは対立行動強化法とも呼ばれ、問題行動と物理的に同時にできないような行動を強化することで、問題行動を減少させる行動変容の手法のひとつです。
DRIは問題行動へのアプローチ法として非常に有効な手段です。
・爪を噛む子に手遊びを教えて、その行動を強化する。
→爪を噛むことと手遊びは同時にできない。
・走り回る子にお絵描きセットを与えて、その行動を強化する。
→走り回りながら絵を描くことはできない。
という感じに。
このDRIという方法が優秀なのは、ネガティブな刺激を使わないという点です。
爪を噛む行動を叱るのではなくて、歌いながら手遊びをして「楽しいね!」
走ることを叱るのではなくて、「お絵描きとっても上手だね!次は○○書いてみよっか?」
といった具合に、みんながハッピーになれるのです。
※ただし、問題行動はそれ自体が何らかの刺激によって強化を受けていることがほとんどで、その随伴性を明らかにしなければ、問題行動そのものを完全に消去することは難しい。ただ、DRIによって問題行動の出現頻度が下がる可能性は高い。
DRIでアンガーマネジメントは可能か?
それでは本題です。
DRIでアンガーマネジメントは可能なのか?
もちろん可能です!
人は怒ると、怒鳴ったり、殴ったり、物に当たったりと様々な行動をしますよね。
まずは、怒った時に自分はどんな行動をしてしまうのかを分析します。
怒鳴るなど、大きな声を出してしまうというのであれば、笑う、深呼吸するといった行動が対立行動にあたります。
笑いながら怒鳴ったり、深呼吸しながら怒鳴ったりということは基本的にできませんからね。
手が出てしまうということであれば、その場から離れる、ストレッチするいった行動が対立行動になります。
そして、必ずやらなければいけないことは対立行動を強化するということです。
大人になれば「怒らなくて偉いね~」と耐えた自分を褒めてくれる人はいないと思います。
つまり、自分で自分の行動を強化する必要があるということです。
アンガーマネジメントに成功したら、普段はしない贅沢をするなど、マイルールを作って自分自身を強化することがとっっても重要なのです。
DRIでは怒りの原因をなくすことはできない
DRIを用いたアンガーマネジメントについてご紹介しましたが、これはあくまで怒りを感じたらすることであって、怒りの原因そのものをなくすことはできません。
職場で怒りを感じることが多い、家庭内でよく怒っている…
という方はアンガーマネジメントも大切ですが、その環境を改善する必要があります。
このサイトでは、行動分析学でより良く生きるヒントを発信していますので、ぜひ参考にしてみてください。
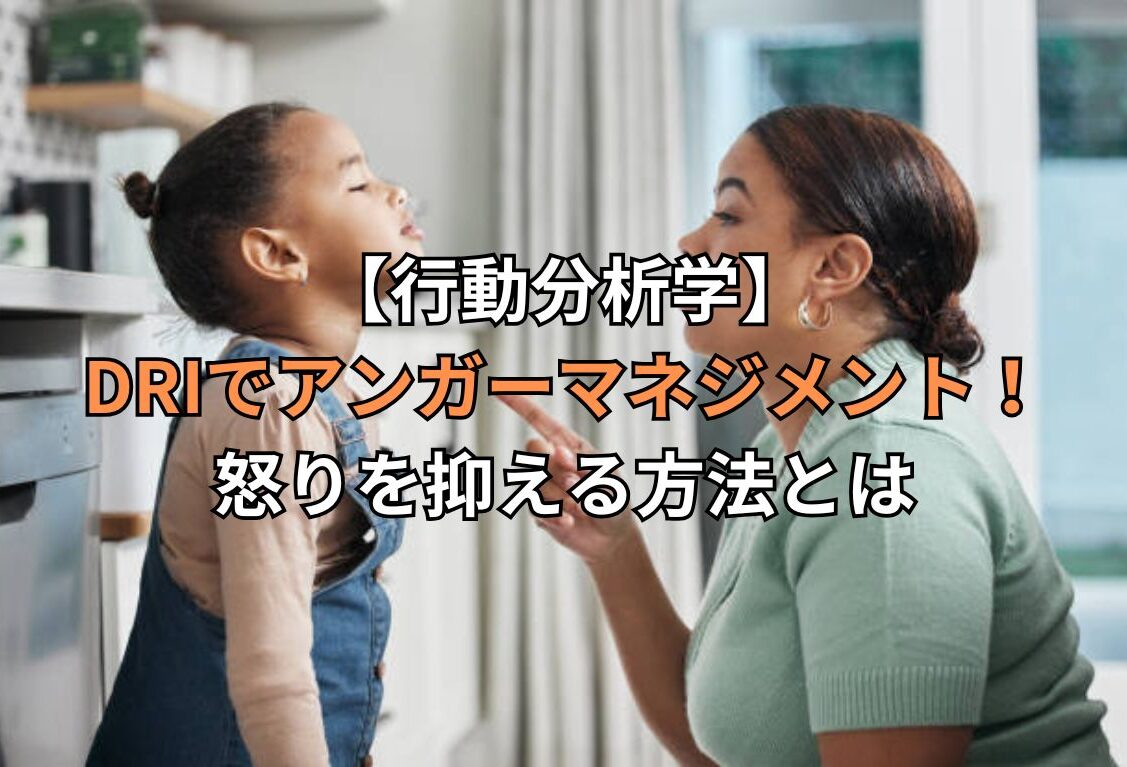




コメント