動物のトレーナーを目指す皆さん、そして現場で活躍されているトレーナーの皆さん、こんにちは!
動物たちの行動問題を解決し、より穏やかで快適な生活を送るために、私たちトレーナーが持つべき重要なスキルの一つに「脱感作(だつかんさ)」があります。

ケンさん(アニマルトレーナー)
アニマルトレーナー歴15年。
行動分析学を応用した近代トレーニングを実施しています。
「行動分析学は世界をより良くする」と信じ、日々発信しています。
脱感作とは?
脱感作とは、簡単に言えば動物が特定の刺激に対して示す過剰な反応…特に嫌悪感や恐怖心を徐々に軽減させていくためのトレーニングテクニックです。
行動分析学の観点から見ると、動物の感情的な反応は過去の経験や学習によって形成されたレスポンデント行動(古典的条件付けによる反射的な反応)として捉えられます。
例えば、過去に雷の大きな音を経験し恐怖を感じた猫は、「雷の音」が「恐怖」という感情を引き起こす刺激となります。
脱感作はこの条件付けられた反応を弱めたり、全く別のポジティブな反応と置き換えたりすることを目的とした応用行動分析の手法と言えます。
雷の音に震え上がる猫の他にも、見知らぬ人に吠えかかる犬や病院に近づくだけでパニックになる鳥など、動物たちは私たち人間には想像もできないほどの多くの刺激にストレスを感じています。
これらの過剰な反応は動物自身のQOL(生活の質)を著しく低下させるだけでなく、飼い主との関係性にも悪影響を及ぼしかねません。
脱感作はこのような問題行動の根本原因にアプローチし、動物たちが刺激に対してより穏やかに対応できるようになることを目指します。
それは単に問題行動を抑制するのではなく、動物自身の感じ方を変えるという点で、非常に重要な意味を持つのです。
脱感作の3つの主要な手法
脱感作には、主に以下の3つの手法があります。
・系統的脱感作(Systematic Desensitization)
・フラッディング(Flooding)/曝露法・洪水法
・カウンターコンディショニング(Counter-Conditioning/拮抗条件付け)
次からは、これらの手法それぞれについて、より深く掘り下げていきましょう。
系統的脱感作(Systematic Desensitization):不安の階段を一段ずつ
系統的脱感作は、行動分析学のレスポンデント条件付けの原理に基づき、動物が特定の刺激(条件刺激)に対して示す不安や恐怖反応(条件反応)を、段階的に、そして慎重に軽減していくための手法です。
系統的脱感作は、恐怖反応を引き起こす刺激の強度を段階的に変化させることで、弱い刺激に対する馴化(habituation)を促し、より強い刺激への反応閾値を上げていくことが目的です。
基本的な考え方は以下の通りです。
不安階層の作成
まずは問題となる刺激に対する動物の不安の度合いを、最も弱いものから最も強いものまで、具体的な状況をリストアップし、不安階層を作成します。
段階的な刺激の提示
作成した不安階層の最も不安レベルの低い刺激を、動物が完全にリラックスした状態で短時間提示します。
恐怖反応が見られなければ、ご褒美を与え、徐々に刺激の強度や提示時間を上げていきます。
焦らずに進める
少しでも恐怖反応の兆候が見られたら、刺激のレベルを下げ、再度慣らすことから始めます。
それでは「犬の爪切り」を例に考えてみましょう
不安階層の作成
①爪切りバサミが遠くに見える
②爪切りバサミが近くにある
③飼い主が犬の足を触る
④飼い主が犬の指を一本持つ
⑤爪切りバサミを犬の爪に近づける(切らない)
⑥爪切りバサミで犬の爪に軽く触れる
⑦犬の爪を一本だけほんの少し切る
⑧数本の爪を切る
⑨全ての爪を切る。
段階的な刺激の提示
まずは爪切りバサミを遠くに見せることから始め、落ち着いていられたらご褒美を与えます。
徐々に爪切りを近づけたり、足に触れたりする練習を行い、最終的に爪を少しずつ切ることに慣らしていきます。

常に動物の反応を注意深く観察し、決して無理強いしないことが重要です。
成功体験を積み重ねることで、犬は爪切りに対するネガティブな感情を徐々に克服していきます。
フラッディング(Flooding)/曝露法・洪水法:短時間で効果を狙う?
フラッディングは、行動分析学の消去(extinction)の原理を応用した手法と捉えられます。
恐怖反応を引き起こす刺激に対する回避や逃避を(物理的に)阻止し、安全な状況が続くことを学習させることで、恐怖反応を減少させることを目指します。
フラッディングは、動物が恐怖反応を引き起こす刺激に曝露された際に生じる逃避・回避反応を(物理的に)阻止することで、その反応が強化されないようにします。
結果として、嫌悪刺激と恐怖反応の間の連合が弱まり、最終的には恐怖反応が消失(消去)すると考えられます。
基本的な考え方としては、回避や逃避ができない状況において、(恐怖反応があったとしても)安全な状況が続くことを学習することで、徐々に慣れるという原理を利用する…つまりレスポンデント消去の手続きを応用しているということです。
短時間での効果が期待される反面、動物にかかる精神的な負担は非常に大きいです。
それではここでも「犬の爪切り」を例に考えてみましょう
①犬をしっかりと保定し、動けないようにします。
②犬が抵抗し、嫌がったとしても、爪を切ります。
③繰り返すうちにそのシチュエーションに対する馴化が進み、恐怖反応を起こしづらくなります。
…ただし、保定するのはどんどん難しくなっていくと思います。

この方法では、絶対に無条件刺激(痛みなど)を提示しないということがポイントです。
重要な注意点
フラッディングは、動物に極めて強い恐怖とストレスを与える可能性があり、心身に深刻なダメージを与えるリスクがあります。
また、飼い主との信頼関係を大きく損なう可能性も高く、問題行動が悪化したり、新たな問題行動を引き起こしたりする可能性も否定できません。
現代の動物トレーニングにおいては、動物福祉の観点からも、特別な状況下を除き、強く推奨されない手法です。
もし検討する場合でも、必ず経験豊富な専門家の指導のもとで行うべきだということを忘れないでください。
カウンターコンディショニング(Counter-Conditioning/拮抗条件付け):ポジティブな感情で上書き
カウンターコンディショニングは、恐怖反応を引き起こす刺激に対して、ポジティブな感情反応を新たに条件付けることを目指す手法です。
カウンターコンディショニングでは、恐怖反応を引き起こす刺激(例:爪切り)と、無条件刺激である好ましいもの(例:おやつ)を対提示することで、恐怖反応を引き起こす刺激に対する反応を、恐怖反応から喜びや安心といった正の感情反応へと書き換えます。
これは、レスポンデント条件付けにおける対提示(pairing)の原理に基づいています。
それではここでも「犬の爪切り」を例に考えてみましょう
①爪切りバサミを見せる直前、または見せている間に、犬が最も喜ぶ特別なおやつを与えます。
②足を触ったり、爪に触れたりする練習中も、継続的におやつを与え、優しい声で褒めます。
③実際に爪をほんの少し切ることができたら、すぐにたくさんのおやつと褒め言葉を与えます。

タイミングが非常に重要です。
恐怖反応を引き起こす刺激が提示されているまさにその瞬間に、最高のご褒美を与えることが効果を高める鍵となります。
ポジティブな経験を積み重ねることで、犬は爪切りへの恐怖反応は減少し、むしろ良いことが起こるサインとして認識するようになる可能性があります。
どの手法がおすすめ?
結論からいうと、現代の動物トレーニングにおいては系統的脱感作とカウンターコンディショニングが最も推奨される手法です。
行動分析学の観点からも、これらの手法は動物の感情反応をより穏やかに、そしてポジティブな方向へと導くための有効な手段であるといえます。
系統的脱感作は恐怖反応を引き起こす刺激への過敏性を徐々に低下させることで問題行動を改善し、カウンターコンディショニングは恐怖反応を引き起こす刺激と好子出現の関連性を形成することで、動物の感情反応そのものを変化させます。
一方フラッディングは行動分析学的には消去の原理を利用しているものの、動物福祉への配慮が不足しており、副作用のリスクも高いため安易に選択すべきではありません。
緊急性の高い状況や他の手法では効果が見られない場合に、専門家の厳格な指導のもとで慎重に検討されるべき最終手段と言えるでしょう。
動物のトレーナーとして、私たちは常に動物の心身の健康を第一に考え、科学的根拠に基づいた、より人道的なトレーニング方法を選択していくべきです。
脱感作は行動分析学の知見を活かし、動物と人間双方にとってより良い共生関係を築くための強力なツールとなります。
それぞれの動物の個性や問題行動の特性を理解し、適切な手法を選択することで動物たちの生活の質を向上させていきましょう!



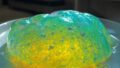

コメント