 行動分析学・動物
行動分析学・動物 【行動分析学】「価値変容の原理」って何?レスポンデント条件付けとの違いを徹底解説!
こんにちは!ケンさんです。今回は行動分析学の中でも少しややこしい「価値変容の原理」について、皆さんが抱くであろう疑問を解消しながら、レスポンデント条件付けとの違いも解説していきたいと思います。価値が変わる?「価値変容の原理」とは皆さんは、普...
 行動分析学・動物
行動分析学・動物  行動分析学・動物
行動分析学・動物  行動分析学・動物
行動分析学・動物  行動分析学・動物
行動分析学・動物  行動分析学・動物
行動分析学・動物  行動分析学・動物
行動分析学・動物 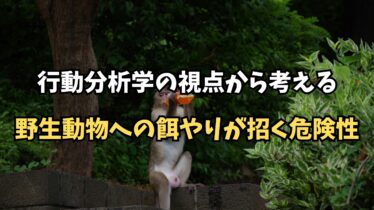 行動分析学・動物
行動分析学・動物  行動分析学・動物
行動分析学・動物  行動分析学・動物
行動分析学・動物 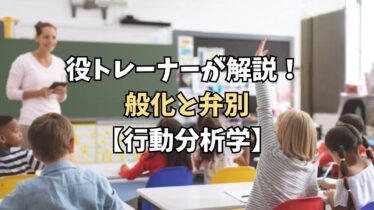 行動分析学・動物
行動分析学・動物